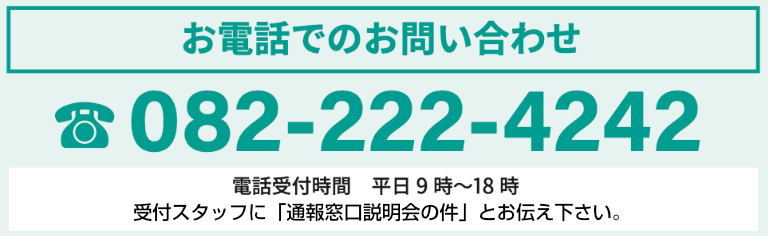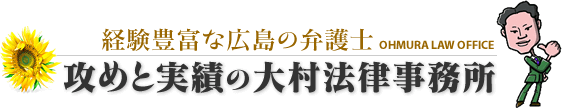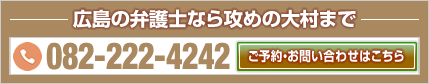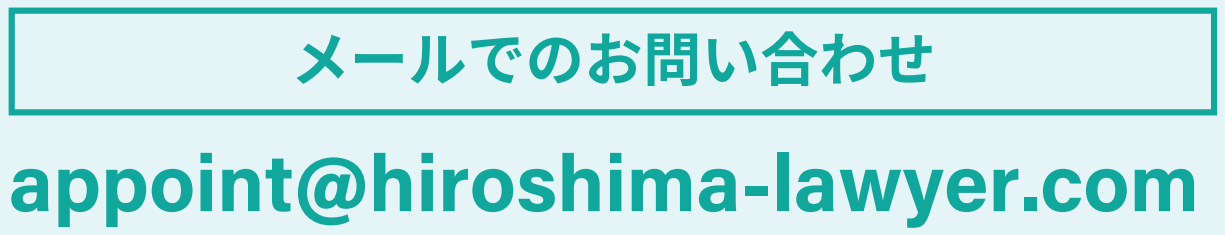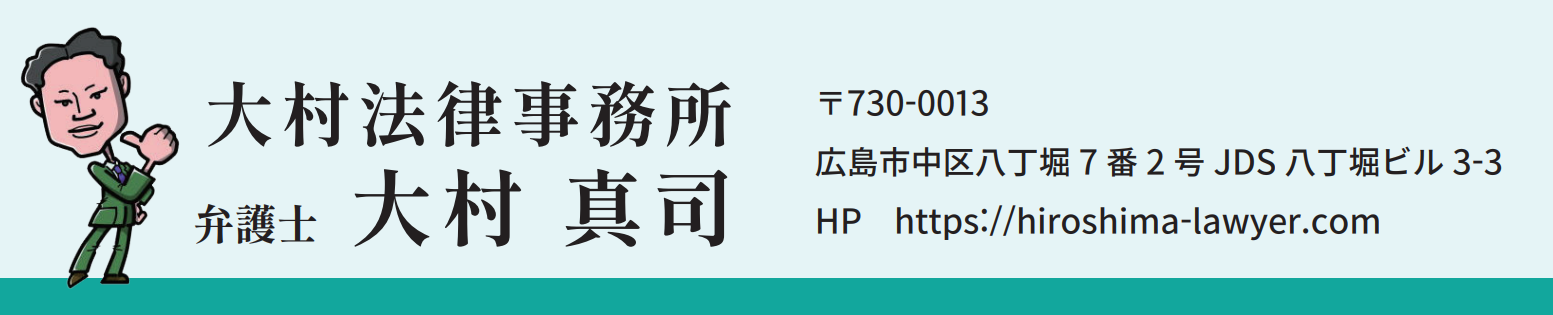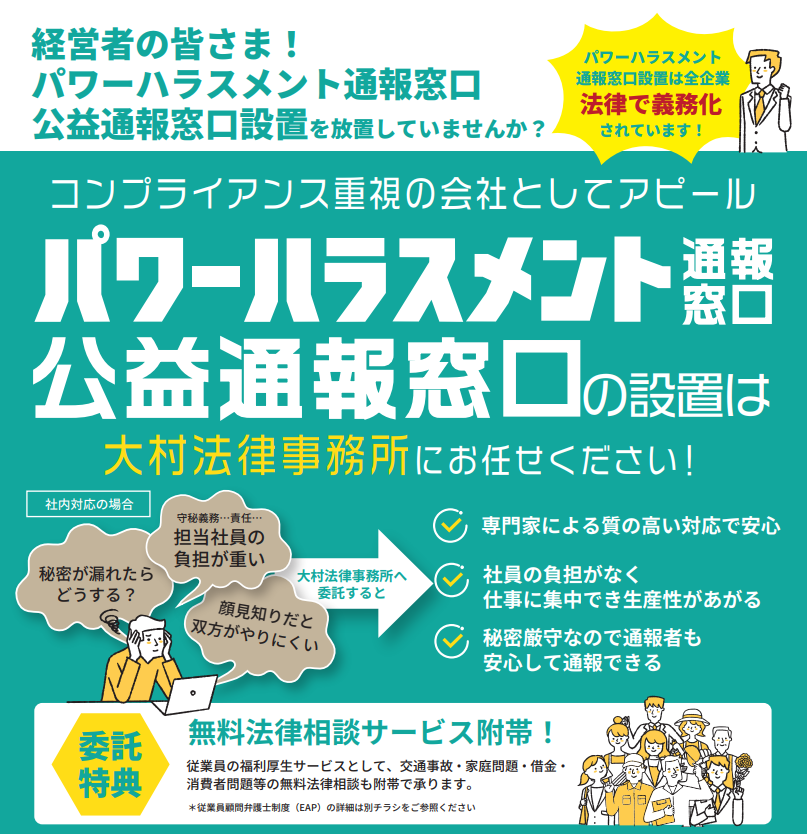
通報窓口の外部委託について動画で説明
パワーハラスメント・公益通報に関する通報窓口の外部委託について、下記動画でわかりやすく説明しています。
パワーハラスメント通報窓口とは

職場におけるハラスメントが社会問題になって久しいところですが、国としても、それに対応するため、労働施策総合推進法(通称・パワハラ防止法)が制定されています。この法律では、いわゆるパワハラにより労働者の就労環境が害されることのないよう、相談に応じたり適切な対策を取れるよう、体制整備などを行うことを義務付けています。(30条の2)。
同条では、パワハラとは、①職場での優越的な関係を背景に、②必要かつ相当な範囲を超える言動によって③労働者の就労環境が害されることを言うとされています。
この法律を受けて制定された厚生労働省の指針によると、事業主は、パワハラを許さないという方針を明確にした上、厳正に対処する旨を就業規則等で明文化すること、相談窓口を定めることなどが求められています。いずれも、単に整備するだけでなく労働者に対して周知・啓発する必要があります。
制定当初は、この義務は大企業だけの法的義務とされていましたが、現在(2022年4月以降)では、この義務は、会社の規模を問わず、全事業者の義務です。
しかし、実際には、かなり大きな会社でない限り、きちんとした体制が整備できている会社は少ないのではないでしょうか?
なお、パワハラの通報窓口というと、悩む従業員の相談を聞く福利厚生サービスというイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
目的は、相談に応じること自体ではなく、その上で適切な対策を取ること。つまり、コンプライアンス経営の一環として、パワハラを撲滅することです。
そのためにまず必要なのは、社内にパワハラが存在しないか常に情報収集することです。その手段として、通報窓口を設置することが求められているのです。
公益通報・内部通報窓口とは

公益通報とは、会社の役員や従業員が一定の犯罪行為・違法行為をしている(あるいはしようとしている)場合に、それに気づいた社内の人が会社や監督官庁等に通報することです。会社ないしはその外部委託先等に通報することを内部通報、監督官庁やマスコミ等社外に通報することを外部通報と言います。
言うまでもありませんが、組織的な犯罪行為は許されません。特に、インターネットにより情報があっという間に拡散し永続するようになった現代では、不祥事を放置すれば、会社の存続に関わりかねないダメージになります。だからこそ、大企業は、気付いた段階で、自ら不祥事を対応策とともに公式発表します。
なお、公益通報者は、会社に害をなす者というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。なぜなら、公益通報の対象事実の多くは、会社組織の一部で起こるものだからです。
例えば、功を焦った開発担当者がデータを改ざんしたり、架空取引により部署の売上成績を大きく見せたりといったことです。
また、個人レベルの不正も少なくありません。通報対象には、水増し請求によるキックバックの受取り、管理職の横領、残業代や立替交通費の不正受給等、会社に直接損害を与えるような個人レベルでの不正も含まれます。これらは会社も根絶したいと考えていると思います。こういった行為は、直属の部下などの通報がなければ見つからないケースも多いでしょう。その部下は、そのことを許せないと思っているかもしれません。上司を飛び越して通報できる窓口があることで、早期発見に繋がります。そうすれば、会社の損失を最小限に抑えることができます。
公益通報についても、公益通報に対応する担当者を定めるとともに、通報窓口を整備する法的義務があります(公益通報者保護法11条1項、2項)。
ただし、この義務が法的義務として課されるのは今のところある程度の規模の会社のみで、従業員300人未満の会社については努力義務にとどまります(11条3項)。
では、努力義務なら、設置しなくてよいのでしょうか?私は、できる限り設置するべきだと考えています。なぜなら、上記のような、不正の早期発見のメリットがあるからです。
また、内部通報窓口がなければ、いきなり外部窓口への通報がなされるリスクが大きくなり、適切な是正の機会を奪われてしまいます。これは、顧客等に不利益が生じるような不祥事、特に組織的不正と糾弾されかねない規模の場合には、企業の存続を左右するような致命的痛手になりかねません。
自分の会社が中小企業だとしても、大企業と取引していれば、その企業から取引停止を受ける可能性はあるのです。
横領や不正受給などの個人レベルの不正については、外部通報されることはあまりないかもしれませんが、長期間にわたり発見されないために会社自体の直接損害が大きくなる危険性が高くなってしまいます。経理を一手に引受けていた従業員が長年横領していた、累積が何千万、というような事例は、弁護士をしていると時折遭遇する事件です。決して他人事ではありません。
このことからすれば、中小企業にとっても、内部通報窓口を整備するメリットは十分あると言えるでしょう。ハラスメントの通報窓口は全企業が作らなければならないのですから、どうせ設置する必要があるなら、公益通報窓口も一緒に設置を検討すべきです。
通報窓口の自社整備と外部委託
ハラスメント通報窓口と公益通報窓口は兼任させるのが現実的
別の法律により設置が義務付けられているハラスメント通報窓口と公益通報窓口ですが、1箇所で両窓口を兼任することは差し支えありません。
両者は全く別の観点から設置が義務付けられていますが、いずれの通報も、通報者の保護の必要性(不利益取扱いの禁止や秘密保持など)や調査における注意点など、ノウハウの共通する部分がありますし、中には双方の対象となる事実もあります(例:暴行や脅迫を伴うような過度の叱責)。
また、通報する側からすると、同一の窓口の方が分かりやすく通報しやすいというメリットがあります。
以上のような点からすれば、窓口を共通にする方が、何かと便利だと思います。
通報窓口の3つのパターン
(内部)通報窓口の整備の仕方としては、①自社で内部整備するパターン②外部委託するパターン③自社整備と外部委託を併用するパターンの3つがあります。
自社整備と外部委託には一長一短ありますから、理想は両方を整備することです。しかし、大企業ならいざ知らず、多くの企業にとって、そこまでのリソースを割くことは難しいのが現実でしょう。
ハラスメント対応も公益通報対応も専門性が高いだけでなく、重い守秘義務を負う上、同僚に対する不利益処分のきっかけにもなる業務です。社内対応する場合、担当者には心理的にも業務的にも大きな負担がかかります。中小企業では、内部の担当者が職務を全うするのは難しいのが現実ではないでしょうか。
逆に、通報しようとする人が、担当者との人間関係から通報を躊躇することも考えられます。中小企業では多くの場合お互いに知合いです。ハラスメントにしても公益通報にしても、通報する方もされる方もやりにくいと思います。
専門家への外部委託
以上のような点からすれば、通報窓口は専門家に外部委託としたうえで、現実に調査すべき事案が発生した場合には、必要に応じて外部委託先のサポートを受けつつ、社内チームを編成して対応することが現実的です。
外部委託先としては、弁護士(法律事務所)が行うパターンのほか、無資格の民間業者と考えられますが、ハラスメント対応も公益通報対応も法律的な専門性が高い業務であることを考えると、法律の専門家である弁護士に依頼する方が安心感が高いと思います。窓口で事情聴取する場合にも、法律を意識して効率的な聞き取りをすることが期待できますし、その後の調査対応にも有益なアドバイスを受けることができます。
顧問弁護士とは別の法律事務所に委託すべき理由
通報窓口の外部委託先として法律事務所を選定する場合、顧問弁護士とは別の事務所に委託することをお勧めします。なぜなら、通報の内容によっては、通報者と会社との利益が対立するケースもあるからです。この場合、一旦通報者に寄り添い対応した弁護士は、利益相反の観点から、会社のために行動することが難しくなる可能性があります。また、通報者にとっても、顧問弁護士が対応するのでは会社のもみ消しに協力するのではないかとの懸念を持ちやすく、相談を躊躇する可能性があります。
顧問弁護士とは別途に費用がかかることは確かに欠点ではありますが、本当に実効性のある通報窓口を設置したいのであれば、顧問弁護士とは別の事務所に依頼するべきでしょう。
以上の観点から、当事務所では、顧問弁護士と通報窓口のいずれかしかお受けしていません。
会社にとっての外部委託のメリット
- 専門的な対応を期待できる
通報窓口業務は専門性が高く、内部に熟練した担当者を配置するのはよほど大きな企業でない限り難しいと思います。
専門家である弁護士に外部委託することで、少ない費用で簡単に専門的な窓口を設置することができます。 - 健全な経営を回復できる
ハラスメントや不正の横行する職場は、業務効率も社内の雰囲気も悪くなります。通報窓口の設置を通じてこれらを是正する体制を整えることで、結果的に、健全な会社としての経営環境を整えることができます。
結果的に、業務の効率化や就労環境の改善につながると言えるでしょう。 - 人材採用の際のアピールポイントになる
中小企業において、通報窓口を外部委託している事務所はまだまだ少数派と思われます。この通報窓口の整備は、会社の健全な経営方針を象徴するものと言えますので、人材採用の際の会社イメージの貢献に寄与します。
特に、当事務所では、従業員に対する福利厚生システムであるEAPを附帯していますので、従業員思いの会社であるということを併せてアピールできます。
※EAPの詳細についてはこちら
人材不足の昨今ですが、賃金よりもワークライフバランスや働きやすい職場を求めるのが最近の労働者の傾向です。この制度の採用により、「ホワイト環境を見える化」することは、人材採用の際アピールポイントにして頂けます。
適切な運用を行うことで、結果的に職場環境が改善し、定着率の上昇も期待できます。 - 取引先からの信頼獲得に役立つ
最近では、取引先の選定にあたり、通報窓口が整備、運用されているかを考慮する会社が増えてきているようです。
消費者庁の調査でも、かなりの割合の企業が考慮している、ないしは考慮することを検討中と回答しているようであり、この傾向は今後益々強まると思われます。
大村法律事務所の外部委託とそれに関連するサービス
- 外部委託
ハラスメント・公益通報の通報窓口として、電話、LINE等で通報を受け付けます。事情聴取は弁護士が行います。
通報があった場合には、通報者、対象者の氏名(通報者から承諾があった場合のみ)、通報の内容、対応の基本的な方針の提案等について、簡易な報告を行います。
なお、当事務所の特徴として、すべての外部委託に、従業員顧問弁護士制度ともいうべきEAP(従業員支援プログラム)のサービスを附帯しています。
EAPの詳細についてはこちら - 通報窓口以外の社内体制の整備
多くの企業では、通報に対応する体制の整備ができていないと思います。
もちろん、窓口は当事務所で行うのですが、社内対応として把握しておかなければならない事項も少なくありません。また、就業規則の見直しや従業員への周知徹底、事案が発生した場合の対応チームの編成方法の決定など、内部の対応体制を整備する必要もあります。
当事務所では、こういった内部体制の整備をサポートします。
※こちらのサービスは有料となります。 - 内部調査チームへの協力
本格的な調査が必要な場合、社内でのチームを編成して対応していただくことになりますが、要領が分からない場合も多いと思います。
弁護士がチームに参加、あるいは後方支援を行うことで、適切な調査が行えるようサポートします。
当然のことながら、通報窓口を社内にも設けられている会社の場合、そちらへの通報をきっかけにした内部調査チームについても、必要に応じてご協力します。
※こちらのサービスは有料となります。
大村法律事務所の通報窓口委託サービスの特徴

- 弁護士が直接、通報窓口として対応
法律上の問題点を把握している弁護士だから効率的で深い事情聴取が可能です。 - 秘密厳守
外部の組織で、かつ守秘義務に厳しい弁護士が対応することで社内への問題の漏洩を防ぐことができます。 - 多様な通報方法
事務所に来所、電話、Zoom、LINE(弁護士直通)など多様な通報方法で対応します。 - 要点を簡潔にまとめて報告
通報内容と弁護士お勧めの解決方針を1枚の報告書に集約。スピーディに問題点を把握し、追加調査の必要性を判断できます。 - 従業員の無料法律相談(EAP)を附帯
当事務所の通報窓口委託サービスには、従業員の法律相談を無料で直接聞く福利厚生サービスを附帯。
EAPの詳細についてはこちら - 当事務所と顧問契約がない企業様限定
事情聴取後に利益相反の問題で弁護士が関与できなくなる事態を最初から回避します。
弁護士費用
通報窓口の外部委託
従業員100人未満の会社 月額3万3000円
従業員300人未満の会社 月額4万4000円
従業員300人以上の会社 月額5万5000円~(別途お見積)
通報体制の整備
原則16万5000円~
現在の整備状況を確認し個別に見積もりいたします。
内部調査チームへの協力
原則3万3000円/1時間
1件当たりの金額でご提案する場合もあります。
通報の流れ
通報窓口の対応は、概ね、以下のようなフローになります。
※②は月額定額料金、③および④は別途個別料金になります。
無料説明会随時開催中!お気軽にお問合せください